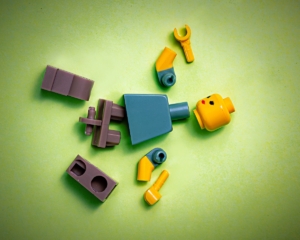スポーツ選手にとって「視力の良さ」は重要だと思われている方も多いのではないでしょうか?
事実、視力はスポーツの成績と関係するとの報告が数多くなされており、「スポーツビジョン」と呼ばれる視力に関する能力を強化するための多彩なトレーニングもトップアスリートを中心に取り入れられています。
ですが、視力が良いこと自体はスポーツに有利に働く可能性があっても、必ずしもスポーツの高い成績には直結しません。
言い換えると、視力がそれほど良くない選手であっても、高い競技成績を上げている場合も存在するからです。
これは、視力検査で評価される視力が、静止状態で細かいものをどのくらい鮮明に見えるかを視力の良し悪しの判断基準としているため、動きの中で利用できる視力とは異なるということを意味しています。

有名な話では、イチロー選手がメジャーリーグのシアトルマリナーズに入団する際に受けたメディカルチェックで視力があまり良くないことを指摘され、メガネなどで強制的に視力を上げることを勧められましたが、プレーに違和感が出るとの理由で断ったそうです。
つまり、イチロー選手の前人未到なヒット数の記録から考えると、スポーツで必要な視力とは、視力検査や動体視力で判断される以上のものが含まれているということになります。
視力は「視覚」として全ての感覚情報と統合して利用されなければ、高い競技パフォーマンスを発揮することには繋がらないのです。

また、視覚のシステムは「意識的なもの」と「無意識的なもの」に分けられ、それぞれ反応時間が異なるという大きな違いがあります。
具体的には、無意識的な視覚システムの反応の方が、約50ミリ秒も素早く反応できるということが、研究の結果によって示されています。(門田ら:2010)
このことは、普段私たちが経験する「勝手に身体が動いた時」と、「意識的に身体を動かそうとした時」の違いと同じであり、勝手に身体が動いた場合の反応の方がより速いことが科学的にも証明されたということになります。
しかし、人間の意識の90%以上を占めると言われている無意識はオートマティックな状態であるため、運動学習の側面から考えると非常に重要なものとなりますが、無意識的な動きの全てが正しい訳ではありません。
特に自身の重心位置や最適な筋出力の調整などに関与する能力「内的認識力」は、競技パフォーマンスに重要な無意識的な動きの精度にも大きく影響します。
競技中に歯を食いしばるなど、いわゆる力みが強い状態では、筋紡錘と呼ばれる筋の張力に反応するセンサーの感度が低下するため、この「内的認識力」は上手く働かなくなってしまいます。

例えば、水の入ったペットボトルの重さを確認するのに、血管が浮き出るくらい全力でペットボトルを握って把持した時と、卵の殻が割れないようなつもりでペットボトルを優しく包み込むように把持した時とでは、どちらが重さを認識しやすいでしょうか?
実際に行っていただくと、答えを言うまでもなく、その差は歴然ですよね。
<まとめ>
・ 視力検査などで評価される「いわゆる視力」は競技パフォーマンスに直結しない
・ 視力は「視覚」として全ての感覚情報との統合が必要
・ 視覚は「無意識的なもの」の方が意識的なものより反応が速い
・ 視覚のシステムには「内的認識力」が深く関わっている
普段見落としがちな「視覚」について考えてみることで、サッカーのプレーにも良い影響があるかもしれませんね。
最後までお読みいただきありがとうございました!